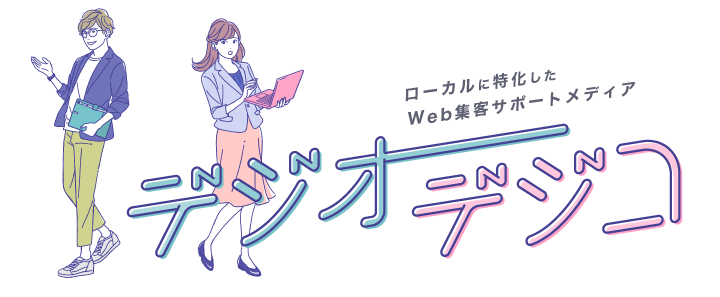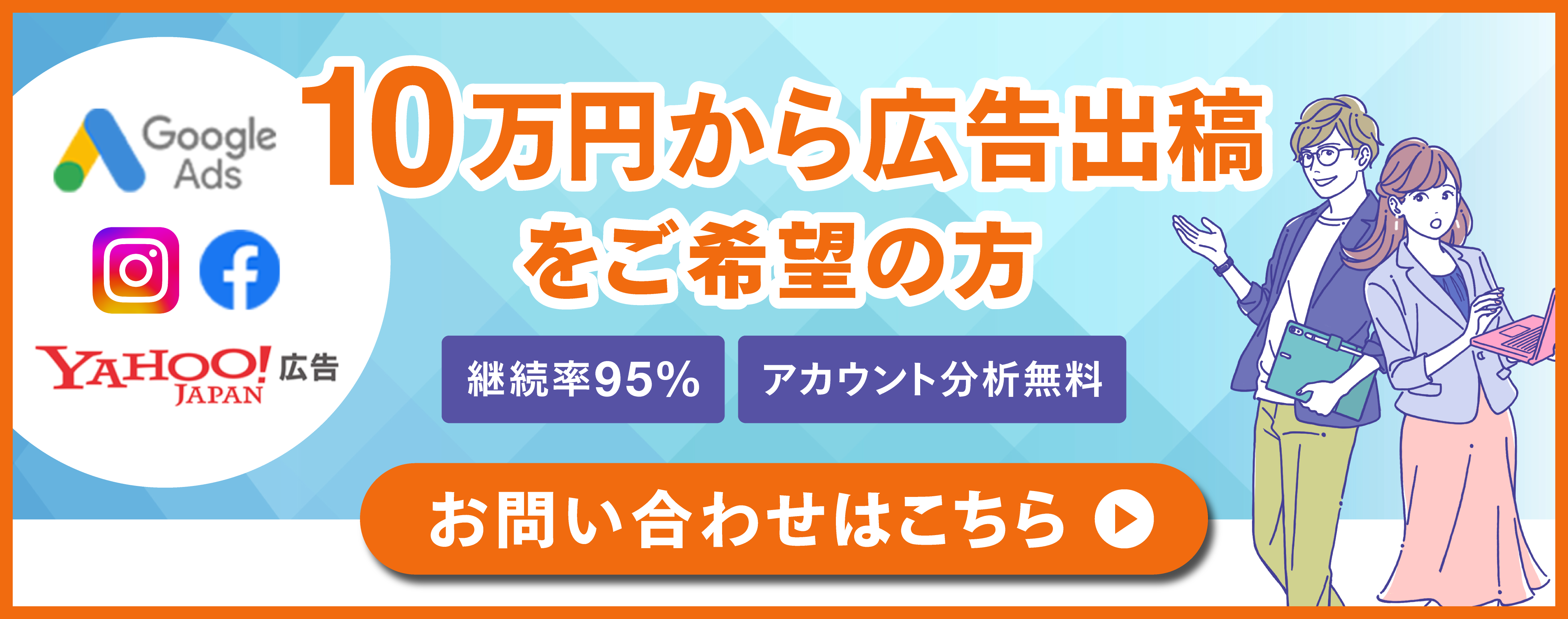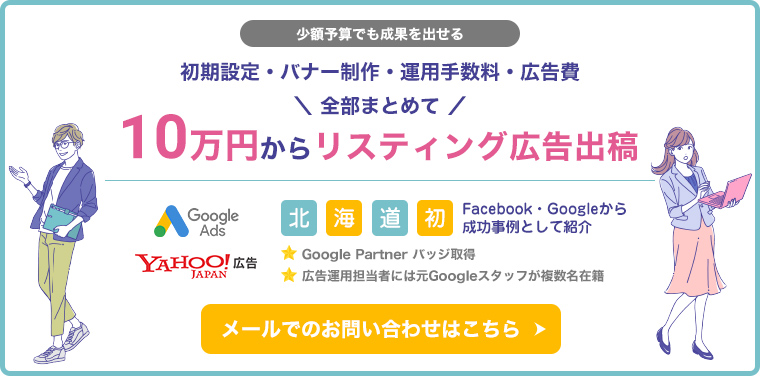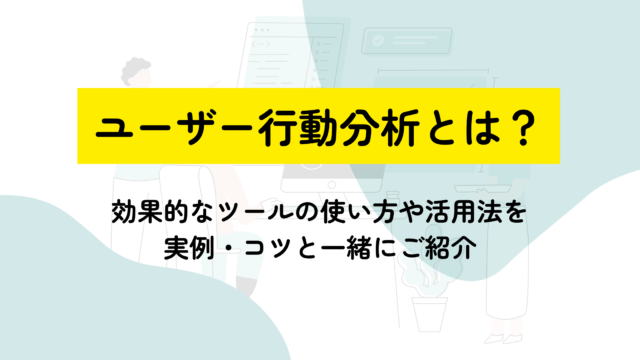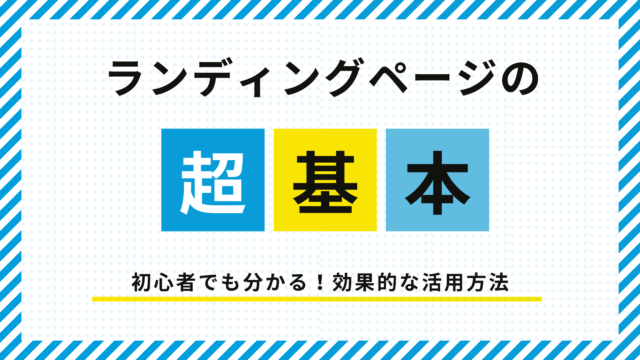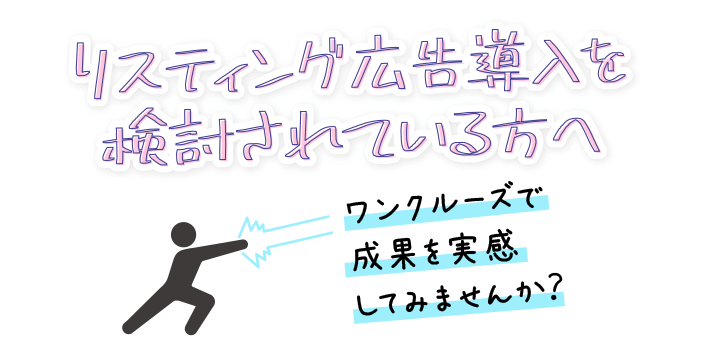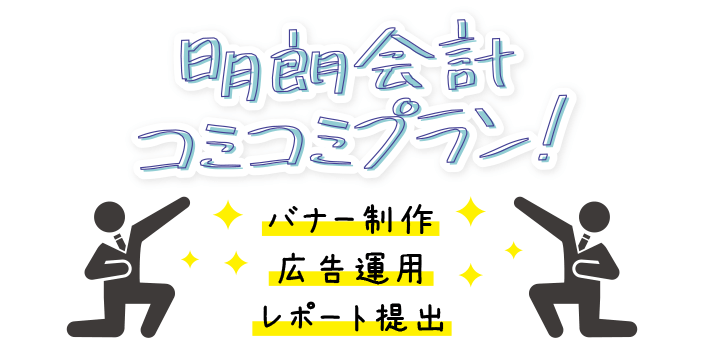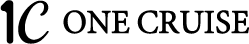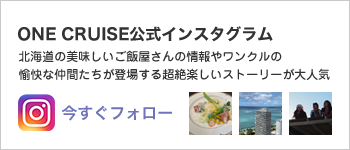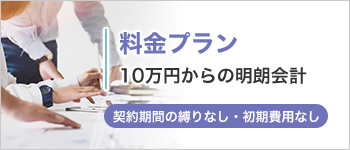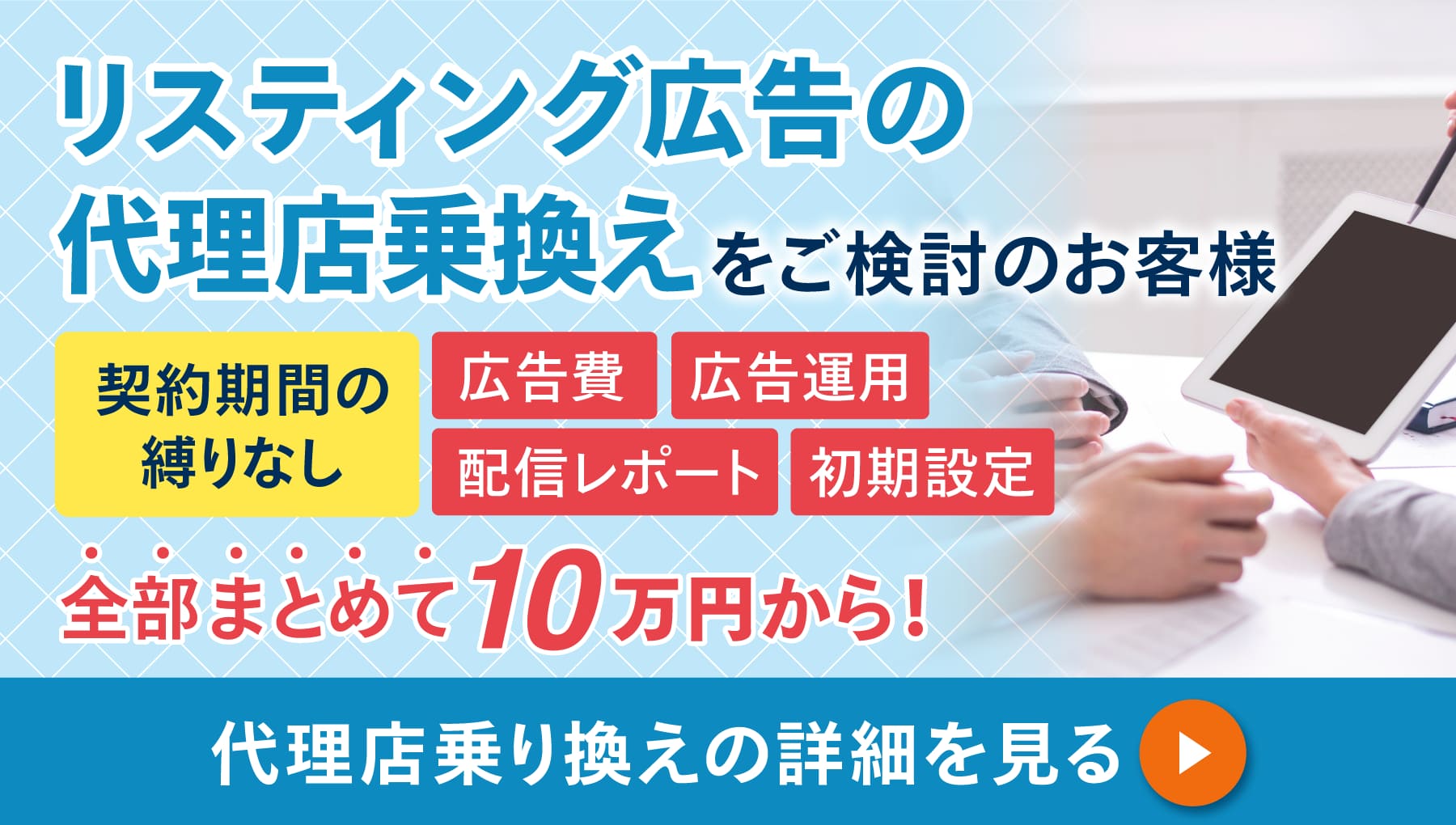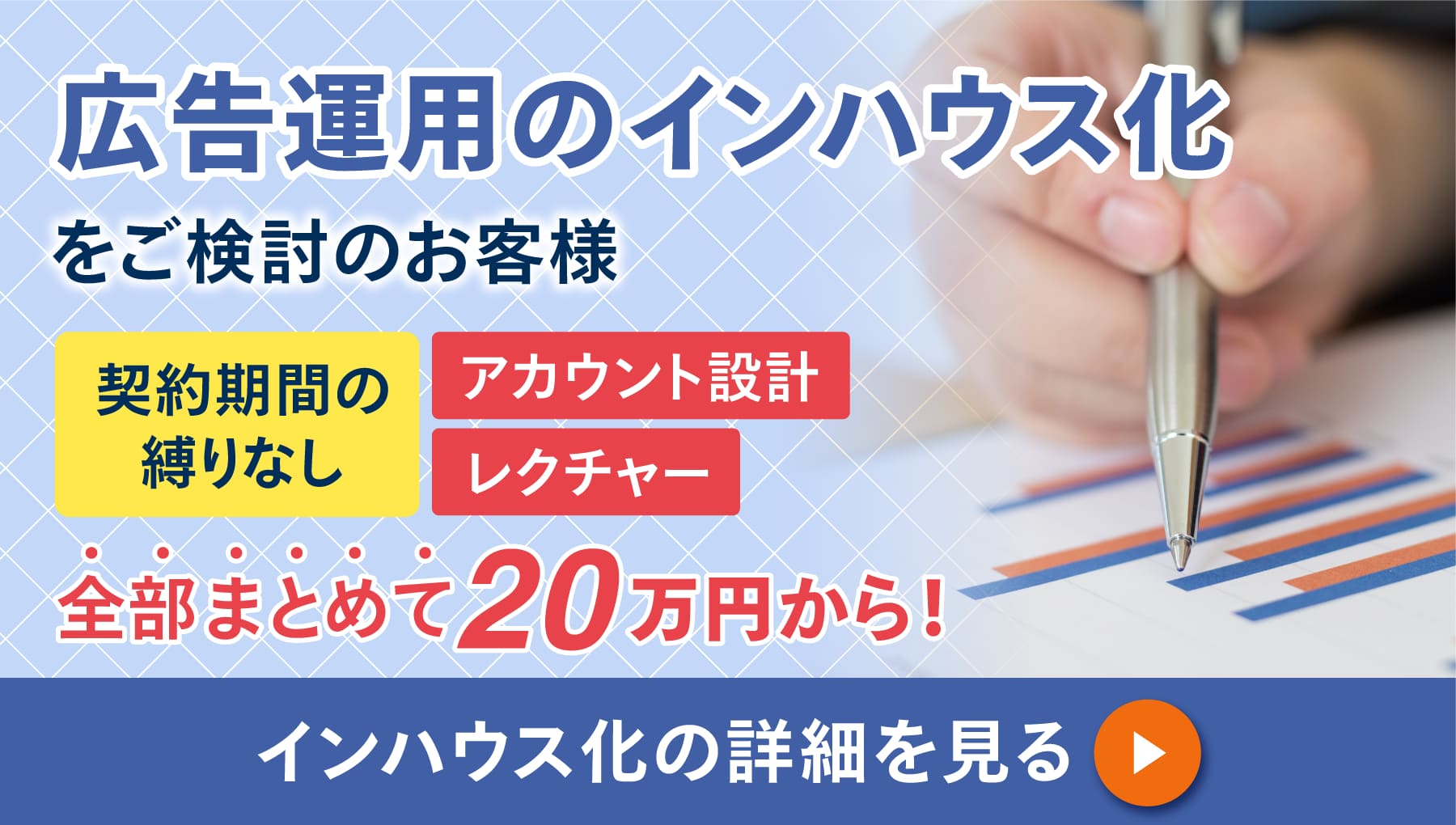直帰率と離脱率の違いとは?
Webサイトのパフォーマンスを分析する際、特に重要視される指標が「直帰率」と「離脱率」です。似ているようで大きく意味が異なるこれら2つの指標を理解することは、サイト改善の第一歩になります。ここでは、直帰率と離脱率のそれぞれの定義と具体的な違いを詳しく解説します。
直帰率とは?
直帰率とは、訪問者がサイトに到達後、最初に閲覧したページ(ランディングページ)だけを見てサイトを離れてしまう割合のことです。つまり、「1ページのみを閲覧してすぐに帰ってしまったユーザー」の割合です。
計算方法は以下のとおりです。
直帰率(%)= 直帰したセッション数 ÷ 該当ページへの総セッション数 × 100
例えば、あるページに100人が訪れ、そのうち40人が他のページへ移動せずにサイトを去った場合、そのページの直帰率は40%となります。
離脱率とは?
離脱率とは、特定のページがユーザーの閲覧セッションの最後になった割合を示します。つまり、そのページを見た後にサイトを離れたユーザーの割合のことです。直帰率と違い、離脱率は「ユーザーがサイト内で複数ページを閲覧した後に最終的に去ったページ」も対象に含まれます。
計算方法は以下のとおりです。
離脱率(%)= 該当ページでの離脱数 ÷ 該当ページの閲覧数(ページビュー数) × 100
例えば、特定のページが200回閲覧され、そのうち60回そのページが最後になった場合、そのページの離脱率は30%です。
「直帰」と「離脱」の具体例から見る違い
直帰と離脱の違いを具体的なケースで比較します。
- 直帰の例: 検索エンジンからユーザーがある記事ページに訪問したものの、内容が求めていた情報と異なったため、そのままサイトを去った場合が「直帰」に当たります。
- 離脱の例: 一方、ECサイトでユーザーがトップページから商品一覧ページ、商品詳細ページと複数ページを閲覧した後、カートに入れずにそのままサイトを去った場合、「離脱」となります。
つまり、「直帰」は入口と出口が同一ページ、「離脱」は入口ページと出口ページが異なるケースが多いという点で区別できます。直帰率は主にランディングページの改善、離脱率はサイト全体の導線改善に役立つ指標です。
直帰率・離脱率の目安となる数値と業界別平均値
直帰率と離脱率を改善するためには、自社サイトの数値が一般的に高いのか、それとも平均的な範囲に収まっているのかを判断する基準を持つことが重要です。ここでは、サイトの種類別および業界別の平均的な直帰率と離脱率について具体的な数値例を挙げながら解説していきます。
サイト種類別の直帰率・離脱率の平均値
サイトの種類によって直帰率・離脱率は大きく変動します。一般的な目安となる平均値は以下の通りです。
ブログ・メディア系サイト
- 直帰率:約70%〜90%
- 離脱率:約60%〜80%
ブログやメディアサイトは1ページのみの閲覧で必要な情報が完結するケースが多いため、直帰率は高めに出る傾向があります。
コーポレートサイト
- 直帰率:約40%〜60%
- 離脱率:約30%〜50%
コーポレートサイトでは、会社情報やサービスページを複数閲覧するユーザーが多いため、直帰率はブログよりも低めとなります。
ECサイト(ネットショップ)
- 直帰率:約20%〜50%
- 離脱率:約30%〜60%
ECサイトの場合、複数の商品を見比べたり、購入プロセスを進める傾向があるため、直帰率は比較的低くなります。ただし、決済プロセスなど途中での離脱率が高まる傾向があります。
業界ごとの直帰率・離脱率の目安一覧
業界別でも直帰率・離脱率の基準は異なります。代表的な業界の平均値は以下の通りです。
| 業界・ジャンル | 直帰率の目安 | 離脱率の目安 |
|---|---|---|
| 飲食・グルメ | 50%〜70% | 40%〜60% |
| 金融・保険 | 40%〜60% | 30%〜50% |
| 医療・ヘルスケア | 50%〜70% | 40%〜60% |
| 不動産 | 40%〜60% | 30%〜50% |
| 教育・スクール | 60%〜80% | 50%〜70% |
| IT・ソフトウェア | 40%〜60% | 30%〜50% |
例えば、金融や不動産業界ではサイト訪問者が比較検討のため複数ページを閲覧する傾向が強いため、直帰率・離脱率は低めになります。一方で教育や飲食業界など、情報が短時間で入手可能なサイトでは、直帰率が高めに出やすい傾向があります。これらの平均値を参考に、自サイトのパフォーマンスを客観的に評価しましょう。
直帰率・離脱率が高くなる5つの原因
直帰率や離脱率が高いとき、その原因を特定することが改善への第一歩です。ユーザーがサイトにとどまらない理由はさまざまですが、ここでは特に多く見られる代表的な原因を具体的に5つ取り上げ、詳しく解説します。
コンテンツの質や量が不十分
直帰率や離脱率が高くなる最も一般的な原因は、サイト内のコンテンツがユーザーの期待に応えていないケースです。ユーザーが求める情報が薄かったり、不明確な場合、ユーザーは短時間で離れてしまいます。
例えば、検索エンジンからの流入が多い記事で、ユーザーが求めている詳細な情報や具体的な回答を提示できていないと、ユーザーは即座に他のサイトへと移動します。反対に、内容が冗長すぎたり、読みづらい長文であったりしても離脱を招く要因となります。
ページの読み込み速度が遅い
ページが表示されるまでに時間がかかると、ユーザーは内容を見ることなく離れてしまいます。特にモバイル端末の利用が増えている近年では、3秒以上の読み込みは離脱を急激に増やす要因になります。
Googleの調査によると、ページの表示速度が1秒から3秒に伸びただけで、直帰率は32%増加するというデータもあります。画像の圧縮やキャッシュ設定などを通じて表示速度を改善することで、直帰や離脱の防止につながります。
UIがわかりにくく、操作性が悪い
サイト内のナビゲーションが複雑だったり、ユーザーが目的のページを簡単に見つけられない場合にも離脱率が高まります。特に、初めて訪問したユーザーが迷わず必要な情報へたどり着ける設計が求められます。
例えば、ボタンやリンクの配置が直感的でなかったり、メニュー項目の名称が曖昧であったりすると、ユーザーはストレスを感じて離脱してしまいます。ユーザー視点でのサイト設計が重要です。
ユーザーの検索意図とページ内容が一致しない
ユーザーの検索意図とコンテンツの内容がズレている場合、ユーザーはすぐにサイトから離れます。例えば「直帰率の改善方法」というキーワードで訪れたユーザーに対して、単に「直帰率とは?」という定義だけの情報しかないと、ユーザーは満足できずに離脱します。
検索クエリに対して具体的かつ適切な情報を提供し、キーワードに応じた適切なコンテンツ設計が必要です。
モバイル対応が不十分(レスポンシブデザインの問題)
スマートフォンやタブレットでのアクセスが主流となった現在、モバイル対応が不十分なサイトは即座に離脱されるリスクが高まります。特に、表示が崩れたり、リンクやボタンがタップしにくい場合、ユーザーはストレスを感じて離れてしまいます。
例えば、PC用のデザインをそのままスマホ画面に表示すると、文字が小さすぎたり、ボタン同士が近すぎて誤タップが増えるなどの問題が生じます。レスポンシブデザインを採用し、どの端末でも快適に閲覧できるよう調整することが必要です。
直帰率・離脱率を改善する具体的な施策と成功事例
直帰率や離脱率の高さは、多くの場合、ユーザーのサイト内での体験の悪さを反映しています。ここでは、直帰率や離脱率を改善するために効果的な具体策を、成功事例を交えながら詳しく解説します。実際に成果をあげた施策を参考に、自サイトでもすぐに改善活動に取り組めるよう具体的なヒントを紹介します。
コンテンツを改善し、検索意図とマッチさせる方法
ユーザーの検索意図に応じたコンテンツを提供することは、直帰率・離脱率の改善に最も効果的な手法の一つです。例えば、ある法律事務所がSEO対策として「交通事故の慰謝料相場」というキーワードで記事を公開していたところ、直帰率が85%を超えていました。その後、「慰謝料の相場」に加えて「実際の事例」「慰謝料を増額する方法」「弁護士相談のメリット」といった、より検索ユーザーが求める具体的なコンテンツを追加した結果、直帰率が約60%まで大幅に改善しました。
検索キーワードからユーザーの具体的なニーズを深掘りし、それに対して最適な回答を与えるようコンテンツを拡充することが重要です。
CTAの最適化でサイト内回遊率を高める施策
CTA(Call To Action)はユーザーが次の行動を起こすきっかけを与えるための重要な要素です。CTAが適切でない場合、ユーザーは次の行動を起こさずに離脱してしまいます。
あるBtoB企業では、サービス紹介ページの直帰率が高く課題となっていましたが、CTAの文言を「お問い合わせはこちら」から「無料資料ダウンロード」や「料金プランを見る」といった具体的な行動を促す内容に変え、さらに目立つ位置に設置することで、サイト内回遊率が40%改善しました。
ユーザーが次に取りたいと思う行動を明確にし、それを適切なタイミングで提示することがポイントです。
ページ速度の改善による直帰率の低下事例
ページ速度の改善は、ユーザーの離脱を防止するための基本的な施策です。とくにモバイルページでは効果が顕著です。
あるファッションECサイトでは、ページ読み込み時間が4〜5秒かかり、直帰率が60%を超えていました。画像ファイルの圧縮や不要なスクリプトの削減、キャッシュの最適化を実施した結果、読み込み速度が約2秒まで短縮されました。その結果、直帰率が約20%減少し、購入率も15%上昇しました。
ページの読み込み時間を改善するためには、GoogleのPageSpeed Insightsなどのツールを活用して具体的な改善ポイントを特定することが有効です。
モバイルユーザーを意識したUI改善施策
モバイルユーザー向けのUI改善も直帰率や離脱率の低下に大きく貢献します。ある教育サービスサイトでは、モバイル対応が不十分でページが見づらく、ボタンのクリック率が低迷していました。そこでモバイル画面におけるボタンのサイズや配置を見直し、さらにフォーム入力を簡略化してUXを大幅に改善しました。その結果、スマートフォンからの直帰率が65%から48%にまで下がり、フォーム送信率が約30%アップしました。
モバイル端末での使いやすさや見やすさを徹底的に改善することで、ユーザーのストレスを軽減し、直帰や離脱を大幅に抑えることができます。
Googleアナリティクス(GA4)を使った直帰率・離脱率の分析方法
直帰率や離脱率の改善には、まず現状を正しく分析し、問題となっているページや原因を特定する必要があります。そのために最適なツールがGoogleアナリティクス(GA4)です。ここではGA4を使った具体的な分析方法と、直帰率・離脱率の改善につなげるための効果的な分析ポイントを詳しく解説します。
GA4での直帰率・離脱率の確認方法と設定
GA4では、従来のユニバーサルアナリティクス(UA)と異なり、標準レポートで「直帰率」という項目は初期状態では表示されていません。ただし、簡単に設定・確認が可能です。
GA4で直帰率を確認するには、次の手順を行います。
- GA4の管理画面にログインし、「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」を開きます。
- 表示される表の右上にある「指標を編集」をクリックします。
- 「直帰率」という指標を選択し追加することで、直帰率が確認できるようになります。
離脱率を確認する場合も、同様にGA4のカスタムレポートや探索レポートで指標として追加することで表示できます。離脱率は「離脱数 ÷ ページビュー数 × 100」で自動計算されます。
具体的に見るべきポイントは、直帰率や離脱率が特に高いページを特定し、それらがランディングページとして適切か、ユーザーが求める情報を提供できているかを分析することです。
GA4の直帰率・離脱率を改善につなげるための分析ポイント
GA4を使って直帰率・離脱率を改善につなげるためには、数値だけでなくその背後にあるユーザーの行動を分析することが重要です。特に注目したいポイントは以下の通りです。
ランディングページ別の直帰率分析
ランディングページごとの直帰率を比較し、特定のページで直帰率が突出して高い場合、そのページのコンテンツやユーザーの検索意図とのズレを疑います。ランディングページのコンテンツが検索意図と合っているか、CTAが適切に設置されているかを確認します。
デバイス別の直帰率・離脱率の比較
GA4ではモバイル・PC・タブレット別に直帰率・離脱率を比較できます。デバイスごとに大きな差がある場合、モバイル対応が不十分であったり、特定のデバイスでページ速度が遅い可能性があります。その場合は、レスポンシブデザインや表示速度改善など、デバイスごとの施策を行います。
ユーザー行動フローの分析
「探索レポート」の「パス探索」を使って、ユーザーがどのページから離脱しているかを視覚的に把握できます。離脱が多いページが購入ページなど重要なポイントである場合、その前のページやCTAの設置方法などを見直す必要があります。
このように、GA4の数値をただ見るだけでなく、具体的なユーザー行動にまで踏み込んで分析することで、サイト改善の効果的な施策が明確になります。
よくある質問
サイト分析をしていると「直帰率」や「離脱率」についての疑問や迷いが生じることがあります。ここでは、多くの方が疑問に感じる代表的な質問をピックアップし、具体的かつ分かりやすく解説していきます。基本的な違いや分析方法、SEOへの影響まで、実践的に理解できる内容をまとめました。
直帰率と離脱率の違いは何?
「直帰率」は、ユーザーがサイトに訪問した後、最初に閲覧したページのみでサイトを離れてしまった割合を示す指標です。一方、「離脱率」は特定のページが、ユーザーが最後に閲覧したページになる割合を表しています。つまり、直帰率は入口と出口が同一ページであるのに対し、離脱率は複数ページを閲覧した後にそのページで終了したケースも含まれる点が大きな違いです。
直帰率の目安はどのくらい?
直帰率の目安はサイトの種類によって大きく異なります。一般的に、ブログや情報系サイトであれば70%〜90%程度が目安で、特に問題のない範囲です。一方、コーポレートサイトやECサイトの場合、40%〜60%以下が理想的な範囲となります。自社サイトの直帰率を業界の平均値と比較し、それを目安に改善を検討することが大切です。
GA4での直帰率・離脱率の見方を教えて!
GA4では直帰率や離脱率は初期設定では表示されませんが、簡単に追加できます。具体的には、GA4の「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」から、「指標を編集」を選択し、「直帰率」や「離脱率」を追加すれば表示可能です。また、「探索レポート」でも詳細な分析が可能で、ページ別や流入経路別、デバイス別の数値を確認できます。
Googleアナリティクスの「離脱」と「直帰」の違いを具体的に教えて!
例えば、ユーザーが検索エンジンからサイトにアクセスし、そのページだけを見てサイトを去るケースが「直帰」です。一方で、トップページから商品ページ、次にお問い合わせページまで閲覧した後にサイトを去る場合、最後のお問い合わせページでの離脱率がカウントされます。「直帰」は「1ページのみ」、それ以外が「離脱」と覚えるとわかりやすいでしょう。
直帰率や離脱率はSEOに影響する?
直帰率や離脱率そのものは、Googleの公式発表ではランキング要素とは明言されていません。しかし、ユーザーのページ滞在時間が短く、すぐに戻ってしまう(直帰が多い)場合、検索エンジンはコンテンツの質や関連性が低いと判断し、間接的にSEOに悪影響を及ぼす可能性があります。ユーザー体験を改善することで間接的にSEO評価が高まるため、直帰率や離脱率を意識した施策は重要です。
直帰率・離脱率が高くても問題ないケースはある?
直帰率や離脱率が高くても、必ずしも問題とは限りません。例えば、ニュースやブログなど、ユーザーが特定の記事や情報を閲覧しただけで目的を達成できる場合、直帰率が高くても自然な現象です。ただし、ECサイトや問い合わせ獲得を目的としたサイトの場合、直帰率や離脱率の高さは明らかな問題です。自サイトの目的に応じて適切な判断が必要となります。
ワンクルーズのリスティング広告運用は、10万円/月(税別)から可能です。
10万円の中には、出稿費用・初期設定・バナー制作費・運用手数料まで全て含んでおりますので、乗り換え費用やアカウント構築費用等は一切かかりません!
ワンクルーズは、Google社から成功事例として紹介されただけでなく、
創業以来、契約継続率90%を維持しており、1,000を超えるアカウントの運用実績があります。
契約は1ヶ月単位で、期間の縛りは一切ございません。手数料の安さをうたう業者もあると思いますが、重要なのは費用対効果!
そこに見合う信頼できる業者をお探しなら迷わずワンクルーズへご相談ください!
おすすめの記事一覧
- 良い代理店か否かを見極める13個のポイント
- インスタグラム広告出稿におけるおすすめの媒体
- 中小企業がネット広告代理店を選ぶ時に比較すべき5つのポイント
- インターネット広告で効果が出ない時に見るべきチェックポイント